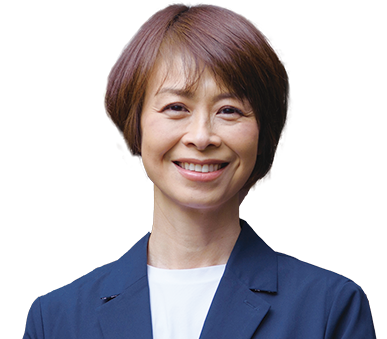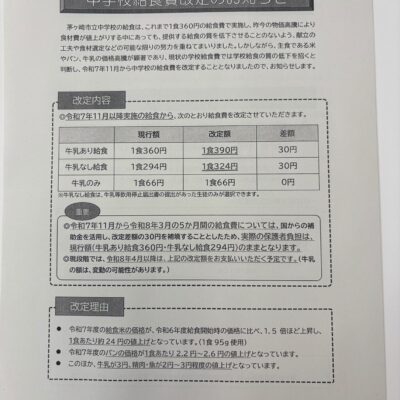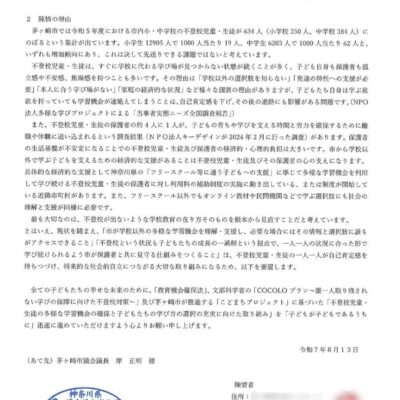6月9日(月) 一般質問2
2.学校支援体制といじめ対応の整備について
現在、学校現場では、いじめや不登校、発達支援など、子どもたち一人ひとりに寄り添った対応が求められており、支援の内容や求められる専門性は年々複雑化・多様化しています。
そうした中で、教員だけでは対応が難しいケースに対しては、ふれあい補助員、スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)など、多様な立場と専門性を持つスタッフが、それぞれの役割を担いながら学校運営に関わっています。
一方で、こうしたスタッフの職務内容や責任範囲、指示系統が学校ごとに異なっている実態があり、現場での運用にばらつきがあるとの声も聞かれています。
さらに、勤務形態や訪問頻度、情報共有の方法に課題があることから、支援が一貫して行われにくい構造的な問題が背景にあるとも考えられます。
また、いじめ事案の初動対応や保護者との連携においても、「誰がいつ関与するのか」「どのような基準で判断するのか」が明文化されていないことで、対応の遅れや保護者の不信感につながる場合もあります。
SNSの普及により、保護者の声が広がりやすくなった現代においては、学校・家庭・行政が連携しながら、信頼関係を丁寧に築いていくことの重要性が、これまで以上に高まっていると感じています。
そこで、こうした学校支援体制の現状と課題を確認した上で、スタッフの役割整理、いじめ対応体制の強化、保護者との信頼構築、そして市全体での統一的な運用に向けた方針について、順次、伺ってまいります。
(1)学校支援スタッフ(ふれあい補助員・SC・SSWなど)について
1問目:支援に当たるスタッフの役割と配置及び課題について
いじめ事案が発生した際、学校現場において、担任教諭の他に、ふれあい補助員、スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)、さらに法的な観点から弁護士有資格職員などをどのような体制で、それぞれの専門性をどう活かしながら役割分担されているのかを状況を伺います。
ふれあい補助員につきましては、特別な支援を必要とする児童・生徒の学習支援及び生活支援を行うために、131名を各学校の規模や児童・生徒の状況に応じて配置しております。スクールカウンセラーにつきましては、児童・生徒及び保護者の心理的課題の解決に向けたカウンセリングや学校での支援に関するアセスメント等を行うために、県から各中学校区に1名から2名の計18名が配置されるとともに、オンラインで面談を行うスクールカウンセラーが1つの中学校区に配置されております。スクールソーシャルワーカーにつきましては、児童・生徒が置かれた環境への働きかけや関係機関と連携を図るために、市教育委員会に4名を配置し、全校を巡回しております。 弁護士有資格職員につきましては、法的な観点から学校での課題等の解決を支援するために市教育委員会に1名を配置しております。
(2)いじめ対応における判断基準と明文化と体制強化について
1問目:各事案に対し統一した判断基準や運用ルールを明文化するとともに、その策定に専門家の関与を求めるべきと考える
いじめ事案への対応では、当事者の子どもの視点に立ち、初期対応において的確かつ慎重な判断が求められます。 しかし、こうした対応の中でSCやSSWといった専門職の関与については、現状では学校長の裁量によって判断されており、関与の基準や関与範囲が必ずしも明確とはいえません。 専門家の関与が遅れたり、学校ごとの対応方針に違いがあるため、当事者や保護者が納得できない場合があります。また、SCについてはあくまでカウンセリングが主な職務であり、いじめの調査そのものには関与しない立場であるということですが、一方で、第三者委員会の構成や運用ルールも保護者へ明確な説明がない場合には、関係者間での信頼構築が難しくなる可能性もあります。 こうした現状を踏まえ、各事案に応じた専門職の関与や判断体制について、統一的な判断基準や運用ルールを明文化し、全校に共通の枠組みとして共有する必要があるのではないかと考えます。市のお考えを伺います。
本市では、「調べる」「防ぐ」「支援する」の3つの柱をいじめ 事案対応の基本としており、それぞれの柱でどのような対応が 必要とされるかは、事案に応じて異なることから、専門性を有 する職員の活用・介入について、統一的な判断基準や運用ルー ルを明文化することは難しいと考えております。 一方、弁護士有資格職員がいじめ事案の対応に加わる際には、 共通した資料を用いて保護者や関係教職員へ説明しております が、この内容が様々ないじめ事案にも共通する対応の要点であ ることから、今後は、本資料を各学校がいじめ事案に係る初動対応に活用できるようにしてまいります。
(3)保護者との信頼構築と情報伝達の透明化について
1問目:当該保護者との関わりについて問う
いじめや不登校などの深刻な課題に直面した際、学校と保護者との信頼関係は欠くことができません。特に、対応の初期段階における説明の丁寧さや、関与する支援体制についての明確な情報提供は、保護者の安心感と信頼につながる大切な要素です。
実際には「誰が関与しているのか」「なぜ特定の専門家が同席していないのか」といった点が十分に伝わらず、保護者が疑問や不信感を抱くケースもあると聞いています。また、学校内での判断が迅速に共有されなかったり、連絡の行き違いによって、保護者側に「後手に回った」と受け止められる事態も起こりうるのが現状です。 こうした状況を踏まえ、保護者に対してどのように説明を果たしているのか。対応に関わる職員や支援関与理由、不在理由についてを丁寧に伝えているのでしょうか。保護者との情報共有を円滑に行うための関わりについて伺います。
本市では、「茅ヶ崎市いじめ防止基本方針」に則り、各学校においては、いじめを把握した際、関係する児童・生徒等に丁寧に聞き取りを行うとともに、双方の保護者の方に対し、聞き取った内容を正確に伝え、適切な支援を行えるよう努めております。加えて、いじめの解決に向けた対応や指導の内容とともに、 役割や専門性を有する職員がどのように関わるかなどの支援体制についても丁寧に説明するなど、早期解決に向けて、当該児童・生徒保護者に寄り添った対応ができるよう努めてまいります。
(4)今後の改善と市全体での統一的運用に向けて
1問目:支援スタッフの役割や責任範囲をガイドラインとして文書化し、全校に共有する計画について問う
これまでの質問でも確認してきたとおり、学校に配置されているふれあい補助員、スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)、弁護士有資格職員は、それぞれ異なる専門性や勤務条件のもとで活動しながら、子どもたちへの支援やいじめ対応など、学校運営の中で重要な役割を果たしています。 しかし、現場においては、それぞれの役割や責任の所在、関与のタイミング、指示・報告の流れが十分に整理されておらず、関係者間での連携に課題が生じているとの声もあります。 こうした現状について、市としてどのように整理・把握されているのか、課題認識を伺います。
支援スタッフによっては、勤務日や勤務時間に制限があり、 常に情報共有ができる状況にはないことから、学校長の指示のもと、授業間の休憩時間中や日報等により情報共有を行うなどの工夫をしております。 児童・生徒一人一人に寄り添った指導・支援に向けては、支援スタッフを含めた教職員が効果的に情報共有を行い連携することが重要であることから、各学校の児童・生徒指導担当教員が参加する会議やスクールソーシャルワーカーの学校訪問等の機会を通して、チーム学校の重要性について周知しております。
—
(1)学校支援スタッフ(ふれあい補助員・SC・SWWなど)について
2問目:
現在、茅ヶ崎市の小中学校には、ふれあい補助員、SC、SSW、弁護士有資格職員といった多様な専門性を持つ支援スタッフがおり、教員と連携しながら児童生徒の安心・安全な学校生活を支えています。
ふれあい補助員は、日々の学校生活の中で児童生徒と最も身近に接する存在でありながら、勤務時間が限られていることから、教員との打ち合わせや会議への参加機会が少なく、保護者と直接関わることも原則行わない運用となっています。そのため、子どもの様子を把握していても、その情報が十分に共有されにくいという面があると認識しています。
SC・SSWについても、心理的・福祉的支援を担う専門職ですが、いずれも非常勤で訪問日数が限られており、関与のタイミングや役割分担について学校側と十分な共通理解が得られているかが問われています。
法的対応が求められるような複雑な案件においては、弁護士有資格職員の専門的な助言が有効ですが、タイミングや関わり方なども含めた整理が必要です。 こうした連携が十分に図られていなければ、情報の分断や役割の重複といった課題にもつながりかねません。 それぞれの専門性を生かした効果的な支援体制の構築に向けて、市としてどのような整理や連携の工夫に取り組まれているのかを伺います。
学校では、校長のリーダーシップの下、教員を始めとする校内の職員が役割や業務等を明確にするとともに、学校支援スタッフについては、勤務時間に限りがある状況を踏まえ、教育相談コーディネーターや児童・生徒指導担当教員が中心となって日常的に情報を集約したり、管理職同席の下、勤務時間内に支援会議等を設けたりするなど、各学校の実情に応じて連携を工夫しております。
3問目:
弁護士有資格職員の「中立的な立場」について、保護者からは疑問の声が聞こえてきます。改めてスクールロイヤー含め職務内容や制度化がされていないために、認識に行き違いがあると感じています。「弁護士有資格職員」の職務について改めて説明願います。
本市に配置している弁護士有資格職員については、弁護士やスクールロイヤーのように弁護士登録を行っている職員ではなく、専門性を有する職員として、学校に係る多様化・複雑化する課題について、法的な観点から助言、支援等を行うとともに、いじめ事案の調査等については、いじめ防止対策推進法や茅ヶ崎市いじめ防止基本方針に則り、事案の解決に向けて、客観的に状況や情報を整理しております。
4問目:
文科省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」第2節調査組織の構成の検討(2)専門家及び第三者の考え方(23ページ)を引用すると、「重大事態が発生した学校を担当する弁護士(スクールロイヤー、顧問弁護士等)や心理・福祉の専門家(スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等)が重大事態調査に委員として参加する場合、専門家の観点から加わることは適切であると考えられるものの、第三者と位置付けて加えることは適切とは言えないため、別の第三者を確保することが必要である。 この点、専門家を調査組織に加える場合には、専門家でもあり第三者でもある者を加えることが適当と考えられるところ、その場合には、職能団体や大学、学会に対して、直接の人間関係又は特別の利害関係がない公平・中立的な専門家の推薦を依頼し、任命することが考えられる」とありますが、弁護士有資格職員の対応について市の見解を伺います。
国の「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」の改訂を受けて、いじめ重大事態調査に弁護士有資格者を派遣する際は、保護者の方に「第三者」ではなく「専門家」として派遣していることを説明しております。また、「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」では、 第三者を加えた調査組織となることが「望ましい」とされていることから、専門家かつ第三者を調査組織に加えることについては、保護者等の希望などの状況に応じて対応してまいります。
5問目:
学校長や教員の裁量によって、支援の関与の範囲や指示の出し方が異なるケースも見られます。その結果、専門性を持つ人材が十分に活用されず、支援が断片的になってしまうこともあります。ふれあい補助員、SC、SSW、弁護士有資格職員といった各職が、どのように連携し、情報共有や意思決定の流れをつくっているのかを把握することは、適切な対応の土台になると考えます。 こうした観点から、教員やスタッフの責任の所在、指示・報告の流れについて、現状を伺います。
いじめ事案に係る対応を含めた児童・生徒への指導・支援・相談については、学校の教育活動全体を通じて、学校支援スタッフを含めた全ての教職員が、校長のリーダーシップの下、共通理解をもち、それぞれの役割等を明確にして、チームとしての体制を構築しているところです。 児童・生徒の様々な事案や課題については、情報を集約、支援会議等において対応の進捗状況の報告、方針や手立てを明確にしているところです。
6問目:
今後、連携体制をより効果的に機能させていくために、市としてどのような整理・改善の方向性を描いているのか検討状況を伺います。
校内の指導・支援・相談に係るより良い連携体制の構築については、各学校の課題を踏まえて、スクールカウンセラー連絡協議会、特別支援教育担当者会、児童・生徒指導担当教員研会等で、今後も情報共有を継続するとともに、指導主事等が学校における具体的な事案への対応について適宜、支援・助言することを通して、連携体制を効果的に機能できるよう働きかけてまいります。
(2)いじめ対応における判断基準と明文化と体制強化について
2問目:
いじめの調査報告書については保護者と確認を取り合い合意の元で進められているとされますが、学校と当事者児童生徒と保護者の間は、主に弁護士有資格職員が中心に対応されています。進捗にはお互い相違がないようどのように確認が行われているのか伺います。
いじめ事案の調査にあたっては、事案の内容や状況に応じて、 書面と口頭での確認、どちらの手法も取り入れております。 弁護士有資格職員が対応するいじめ重大事態調査を開始する際のガイダンスにおいては、対象児童・生徒の保護者の方に対して、以前は口頭のみの説明であったものの、令和6年8月に改訂された「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」に基づき、書面による確認も併せて行っております。 また、いじめ重大事態調査の途中経過についても、書面で示し、確認しながら進めております。
3問目:
いじめ対応においては、学校内での調査に加えて、外部の専門的立場からの視点も確保することも重要です。しかし学校主体調査では弁護士有資格職員以外は学校関係者のみで構成されていて、報告書も作成までに数年要するケースもあり、完成時には関わった教員をはじめ関係者や子どもなどが学校に在籍していないという状況で、運用の実効性や透明性に不安があるという声が保護者から寄せられています。
SCは本来「支援目的」であり調査には関与しないということですが、それに代わる外部の専門的な視点が十分に確保されているとは言い難く、「学校長の任命」とされるため委員会の構成や役割分担の明確化が今後の課題と考えられます。茅ヶ崎市として「いじめ調査フロー」が定められていることは承知していますが、現場では運用にばらつきが生じている可能性もあります。 こうした点を踏まえ、第三者委員会の構成の標準化や、外部有識者の積極的な関与を促す体制の整備が必要ではないかと考えます。市の見解を伺います。
構成員の標準化につきましては、第三者委員会の場合、事案の内容に応じて必要とされる専門家は変わりますが、全員が外部の専門家により構成されます。第三者委員会にあたるいじめ防止対策調査会の会長の意見なども踏まえながら、構成員の選定をしてまいります。 また、学校主体調査の構成員については、対象児童・生徒の 保護者の方の意向を確認しながら学校と協議の上、構成員を選定しているところですが、協議に当たっては、構成員に専門家や第三者を積極的に拡充できるよう、関係機関や外部機関とも調整を図ってまいります。
4問目:
市内32の小中学校HPには「学校いじめ防止基本方針」が掲載されています。表紙に改定された年号が記載されていますが、学校によって様々でありますし、基本方針の見直す時期などには触れられておらず保護者からは状況が伺い知れません。「学校いじめ防止基本方針」の見直しや改定年更新のタイミングについて市の見解を伺います。
各学校においては、毎年度「学校いじめ防止基本方針」について定期的に見直し、改訂の必要性について検討しておりますが、基本方針の制定時に想定していなかった事案が生じ、基本方針に記載した対応では解決が難しいと判断した場合や、基本方針に記載されていないことに係る対応で学校が判断に迷った場合、いじめに係る国や県の基本方針が改訂された際は、各学校において十分に協議し、改訂を実施すべきタイミングと捉えております。
5問目:
学校によって「学校いじめ防止基本方針」の内容のボリュームが異なります。いじめ防止に向けた取組などの説明は詳細に記載されていますが、いじめが発生した場合に保護者がまず知りたいのは、それ以降の一連の流れをどう対応してもらえるのか?ではないかと考えます。一連の対応を理解するにはフローチャートが効果的だと思いますが、市の見解を伺います。
いじめ事案が発生した際の、各学校の具体的な対応の流れを フローチャートや簡潔明瞭な表現で示すことは、保護者の方にとっても教職員にとっても共通理解を図りやすいものであると認識しております。 教育委員会といたしましては、各学校がいじめ事案対応の流れを作成する際に、専門性を有する職員が助言するなどして、保護者の方や市民の皆様にとって、より分かりやすいものとなるよう学校支援に努めてまいります。
6問目:
茅ヶ崎市では、いじめ対応の手順として「いじめ調査フロー」が整備されていますが、市教委から市長へ報告は結果が出るまで行われません。報告書が完成するまでに数年が要することのある案件の取り扱いについて、市長への報告に関する基準や判断のあり方について、市としての見解を伺います。
いじめ重大事態が発生した際の市長への報告は、いじめ重大事態調査を開始した段階で「対応開始日」「重大事態事由」「訴えの概要」等を、調査報告書が完成した段階で報告書を市長に提出するとともに、今後の方向性について報告しております。
7問目:
「茅ヶ崎市いじめ調査フロー」や「学校いじめ防止基本方針」の基準なども含めて見直しの検討ができないかと考えますが、市の見解を伺います。
必要に応じて見直しを図っている「茅ヶ崎市のいじめ調査フロー」や「学校いじめ防止基本方針」等、いじめ事案に係る資料については、対象児童・生徒及び保護者の方にとって分かりやすく、見通しを持つことで安心感を得られるよう、また教職員にとっても活用しやすい資料であることが望ましいことから、 今後も、各学校に対して常時検討・修正を働きかけてまいります。
(3)保護者との信頼構築と情報伝達の透明化 ・当該保護者との関わりについて問う
2問目:
保護者が学校や教育委員会の対応に疑問や不安を感じた際、その声がSNSなどを通して広く発信されることもあり、学校や関係機関に対して大きな波紋が広がるケースもあります。特に対応の過程が可視化されていない場合や、説明が不十分と受け取られた場合には、事実関係とは異なる情報が独り歩きしてしまい、結果的には生徒児童や保護者、教員の心情にも影響を与えることにも繋がると考えます。このような状況を防ぐには、丁寧な情報共有とともに、寄り添った対応が重要です。市としてこうしたSNS等による情報発信の影響についてどのように受け止めているのか伺います。
いじめの事実認識や対応方針において、学校と保護者の方との間で認識の違いが生じたり、対応に対する疑問や不安から信頼関係を築けず、さらに保護者の方がSNSなどにより情報を発信し、大きな影響を及ぼす場合があることを認識しております。各学校が事案発生時に、関係する児童・生徒保護者との信頼関係の下、解決に向けて丁寧な対応を心がけるよう、今後も働きかけてまいります。
(4)今後の改善と市全体での統一的運用に向けて ・支援スタッフの役割や責任範囲をガイドラインとして文書化し、全校に共有する計画について問う
2問目:
ふれあい補助員、SC、SSW、弁護士有資格職員について、それぞれの役割や責任範囲、指示系統や報告の流れなどを明確にし、「いじめ防止基本方針」へ文書化した上で、全校に共通の運用ルールとして示していくことが必要ではないかと考えます。 市として、今後「いじめ防止基本方針」の整備や共有について、どのような方向性で検討しているのか、具体的な見解を伺います。
いじめが多様化・複雑化する中、教職員の組織的な対応、対象児童・生徒の安全・安心な学校生活など、どの学校でも一律に対応すべきことに加えて、事案の内容や実情等に応じて、各学校の「学校いじめ防止基本方針」に基づいて、個別の適切な指導・支援を行うことが肝要です。 教育委員として必要に応じて全校で共有できる資料を作成するなど、各学校における「学校いじめ防止基本方針」の改訂等の支援を行ってまいります。