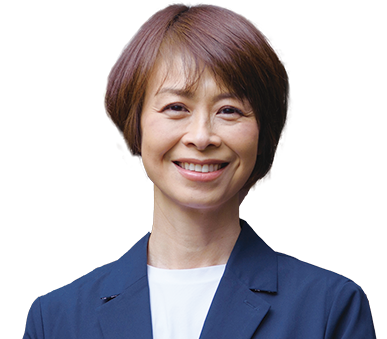一般質問:1.不妊治療における先進医療費助成制度の導入について 4問目
(2)市が導入に至らなかった経緯と判断根拠について
市は今回『国が一律に対応すべきもの』との見解を示していますが、かつて待機児童や小児医療費助成の課題においても『国がやるべき』と繰り返した結果、市が市民の声に応えるのが遅れた経緯があります。
同じ轍を踏むことへの懸念を、私は強く抱いています。
繰り返しになりますが、市民からは「主治医は妊娠のために全力で取り組んでくれるのに、どうしても金銭面で断念せざるを得なかった」「不妊治療は先の見えないトンネルを走るようで、精神的にも肉体的にも、そして経済的にも大きな負担を抱える」といった切実な声が寄せられています。
こうした声は、制度論を超えて、市が真摯に受け止めるべき現実です。
財源や公平性、他の医療分野とのバランスの課題は理解していますが、本市は「妊娠期から切れ目のない支援」を掲げながら妊娠に至る前段階の先進医療への支援は行っておらず、理念との間に空白が生じています。
さらに、コロナ禍を経た人口動態の変化や県制度の創設、市の子育て支援方針の拡充など、制度の導入について検討された当時とは状況が大きく変化しています。
こうした環境変化や現場の声を踏まえ、制度参加や新たな支援策の可能性について、市の見解を伺います。
◆保健所副所長答弁
社会環境の変化や現場の声を踏まえ、県の制度への参加や新たな支援策の可能性について、答弁いたします。
県が、市町村への補助事業を令和8年度で終了することもあり、本市が、新規事業として不妊治療において医療保険の適用されない先進医療への助成事業を創設することは困難な状況です。
本市といたしましては、このような取組は、本来自治体間で差異を生じさせるものではなく、国において全国共通の制度設計を行うべきものと考えております。
県は、令和5年5月に関東地方知事会として「不妊治療等への助成など、妊娠・出産施 策の充実を図ること」を国に要望しており、県の所管課においても「不妊治療に対する 医療保険の適用拡大等」をこども家庭庁に提案していることを確認しております。
こうした県の動きに期待を寄せつつ、本市におきましても、先進医療への保険適用等について、機会を捉え、国へ要望してまいります。
メッセージ受付中!
茅ヶ崎のまちのこと、市議会のこと、みなさんの暮らしの中でのお気づきのことなど、
何かありましたらお気軽にお問い合わせください。
内容をしっかりと拝見し、お返事させていただきます。