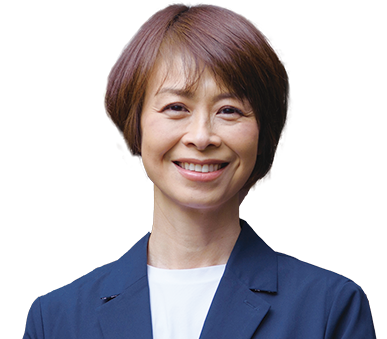【津波警報・振り返りシリーズ vol.3】“南と北の温度差”一律対応の限界?~茅ヶ崎の地理と住民意識のギャップを考える~
今回の津波警報で浮き彫りになったのは、「市内でも、受け止め方に大きな差がある」という現実でした。
茅ヶ崎の地理的構造
・茅ヶ崎市は南北に長く、海に面する南側(国道134号より南)は津波の直接リスクがある地域
・一方で、JR茅ヶ崎駅より北側は標高が高く、津波の到達想定区域外
しかし、今回の警報では
北側でも起きた“間接パニック”
・企業・スーパー・商業施設の一部が閉鎖や早期閉店
・通勤・通学への影響、混乱を懸念した一斉の“自主対応”
・JRの運休により、北部住民や市外の人にも大きな影響が拡大
結果的に、「本来避難の必要がない地域」までが影響を受け、市内全体が“警報モード”に突入してしまったとも言えます。
問い直したいこと
「3メートルの津波予報で、駅の北側まで全部がパニックになる必要があったのか?」
・海側と山側で“リスクレベル”は違うのに、情報は“画一的”に発信され、受け手側も“横並び”で動いてしまう
この一律的な対応は、本来守るべきエリアへの資源集中を妨げ、誤解や混乱を生み出す要因にもなり得ます。
次に活かすための視点
・地域ごとのリスクと行動指針の明文化
→ 「自分の住む場所は避難対象かどうか」を“前もって知る”こと
・公共交通・企業・商業施設と市の連携ルールづくり
→ 一斉に閉めるのではなく“段階的・選択的な対応”へ
・駅を挟んだ情報の棲み分け
→北と南で“異なる情報設計”が必要なのでは?
「正しく怖がる」ことが、防災の基本です。
そのためには、正しく知り、正しく伝える構造が不可欠ですね。
茅ヶ崎の地理に合った“リスク別の防災設計”へ。
これを機に、まちのあり方を見直していきましょう。
メッセージ受付中!
茅ヶ崎のまちのこと、市議会のこと、みなさんの暮らしの中でのお気づきのことなど、
何かありましたらお気軽にお問い合わせください。
内容をしっかりと拝見し、お返事させていただきます。