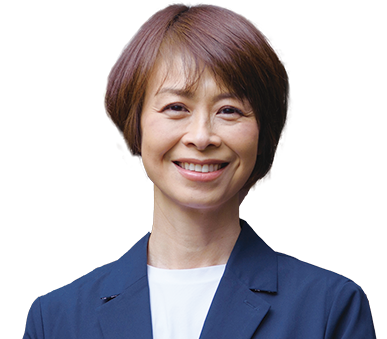【津波警報・振り返りシリーズ vol.4】JRだけ全面運休それは本当に必要だったのか?〜“止める判断”と“動かす責任”を考える〜

7月30日、最大3メートルの津波警報が発令されたこの日、
JR東海道線は朝10時から夜10時までの12時間にわたり全面運休となりました。
一方で、小田急線、相模線、京急や地下鉄など、他の鉄道各社は 通常運転または一時的な点検後の再開 にとどまりました。
対応のギャップが生んだ“市民の混乱”
→「なぜ東海道線、総武線だけ全面ストップ?」
→「再開情報が遅くて動けない」
→「通勤・通学・病院に行けない」
→「帰宅困難者が発生し、滞留も」
“安全のための停止”が、“移動困難と不安”を生み出paradox に…
判断は妥当だったのか?
JR側の判断は「安全第一」に基づいたものでしょう。しかし今回は、津波の発生源は遠方(カムチャツカ沖)→被害は報告されず→他の鉄道は再開済→地元でも被災・冠水等の被害なし→警報から注意報に変わっても再開の目処がつかない
この状況で、12時間の全面運休が本当に市民生活にとって“妥当な判断”だったのか、今後の検証が必要です。
今後に向けた論点
情報連携のあり方として→ 市・鉄道会社・県・国の間で「運休の判断基準と連絡体制」を統一できるか?
段階的運休という考え方→ 危険区域(海岸付近)の一部区間のみ運休/徐行運転などの柔軟対応は?
代替移動手段と支援策の事前整備→ バス・シェアサイクル・一時待機施設の周知など、運休を前提とした“動ける手段”の確保
市民の声として「安全のためのストップは必要」「でも止めるだけで終わってしまうと、生活は守れない」その声が、今回のJR全面運休には多く寄せられました。
“止める判断”と同じくらい、“止めたときの責任”と“その後の動線設計”が、いま問われていると感じます。
#JR運休の影響 #止める判断と説明責任
#鉄道と災害対応 #公共交通と連携の再設計
#こえをチカラに #やさしく強い茅ヶ崎へ
#津波警報振り返り #藤村ゆかり
メッセージ受付中!
茅ヶ崎のまちのこと、市議会のこと、みなさんの暮らしの中でのお気づきのことなど、
何かありましたらお気軽にお問い合わせください。
内容をしっかりと拝見し、お返事させていただきます。