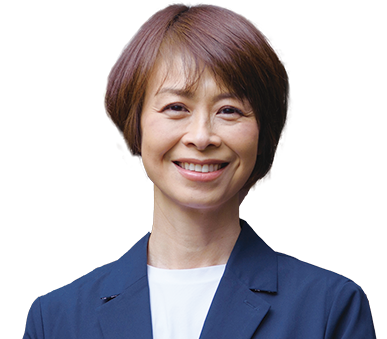6月9日(月) 一般質問
1.放課後児童クラブについて
近年、茅ヶ崎市では、コロナ禍を契機に 都内からの転入者が増加し、それに伴って保育園や幼稚園の利用希望者が増え、子育て支援のニーズが急速に高まっています。
そして、保育園や幼稚園を利用していた子どもたちが小学校に進学すると、放課後の生活の場として放課後児童クラブの利用希望が集中し、需要が拡大しています。
しかしながら、本市の放課後児童クラブの現状は、施設数・定員数ともに十分とは言えず、特に1・2年生の段階で既に定員に達し、3年生以降の利用希望者が待機となるケースが多く見られます。
施設の新設は、財源や用地の確保、さらには学校施設の空き教室の不足といった複合的な要因により、すぐには進めにくい状況です。
また、本市の小学校は学区制であることから、保育園・幼稚園のように施設を広域で選ぶことが難しいという課題も存在しています。
こうした状況下で、保護者の働き方が制限され、特にひとり親家庭では収入減や生活困窮に直結する深刻な影響が懸念されています。
加えて、夏季休暇期間などに設けられるサマースクール等の代替事業についても、情報が十分に届かず、利用できる人とできない人との間で格差が生じている実態があります。
放課後児童クラブは単なる預かりの場ではなく、子どもたちにとっての安心できる居場所、健全な育成の場として重要な役割を果たしています。
本日は、こうした現状を踏まえたうえで、待機児童の実態、人的資源の確保、情報発信のあり方、そして制度全体の改善に向けた取組について、市の見解を伺ってまいります。
(1)待機児童の現状と課題について
1問目:令和7年度の現状と課題について
令和7年度における本市の放課後児童クラブの施設数、総定員(そうていいん)、実利用者数、そして待機児童数の現状について確認させていただきます。
放課後児童クラブにおける現状についてお答えします。令和7年4月1日時点における本市の放課後児童クラブの施設数につきましては、公設民営児童クラブが27クラブ、民設民営児童クラブが9クラブ、合計で36クラブとなっています。総定員数につきましては、公設民営児童クラブが1,746名、民営児童クラブが509名、合計で2,255名となっています。また、実際の利用者数につきましては、公設民営児童クラブが1,705名、民設民営児童クラブが437名、合計で2,142名となっております。
最後に4月1日時点での待機児童数につきましては、260名となっています。
(2)待機児童解消に向けた取組について
1問目:待機児童解消に向けた市の具体的な取組について
待機児童の解消に向けた本市の基本的な方針と目標、そして現時点で進められている具体的な取り組みの内容について伺います。
児童クラブの待機児童解消につきましては、令和5年3月に 策定した「茅ヶ崎市児童クラブ待機児童解消対策(令和5年度 ~7年度版)」に基づき取組を進めているところでございます。 現行の対策では、「基本的な考え方」として「実施計画2025の対象期間である7年度までに、施設整備については小学校3年生までの受け皿を確保するとともに、小学校4年生以上についても安全・安心な放課後の居場所を創出することにより、 待機児童の解消を目指す」こととしています。 現時点で進めている具体的な取組としては、待機児童が多く生じている小学校を中心に、本対策で掲げている「学校施設の利活用」の実現に向けて調整を行っているところです。
(3)指定管理者の指定について
1問目:放課後児童クラブ運営に関する課題認識について
本市では指定管理者制度を導入し、現在は複数の法人が学区ごとに運営を担っています。
近年の指定替えにより、地域保護者(ほごしゃ)主体から全国展開型(がた)の民間法人に運営が移行した地区もありますが、そうした中で、事業者ごとの方針の違いや保護者対応のばらつき、地域との関係性など、どのような課題を認識しているのかを伺います。
放課後児童クラブの指定管理者が複数であることによる事業者間の方針の違い等について、お答えいたします。
公設民営児童クラブの指定管理者につきましては、令和3年度以降、2事業者が指定されておりますが、本市が示す基準に基づき、適切に事業運営がなされているところでございます。 日々の運営について、保護者等から、ご意見等をいただくこともありますが、その都度、それぞれの指定管理者と十分に連携を図りつつ、適宜指導等も行いながら、必要な対応や改善を図っているところでございます。 事業者としての組織風土や特色などはございますが、サービス提供にあたって大きな地域差などが生じることなく、対応できているものと認識しております。
—
(1)待機児童の現状と課題について 順次伺ってまいります。
2問目:
地域別・学年別に見た際、待機児童の偏りや特徴にはどのような傾向があるのか、本市としての分析を伺います。
待機児童数の状況について、はじめに、地域別につきましては、増減に変動はあるものの、大規模な宅地造成やマンション開発等の影響を感じる中、直近5年間、市南西エリアにおいて 増加傾向が続いております。 次に、学年別につきましては、低学年児童ほど入所希望が多く、高学年になるにつれて、心身の発達に応じて過ごし方が変化していく状況も見られ、令和7年4月1日時点では、小学4年生の待機児童が最も多い状況となっています。
3問目:
こうした待機発生(はっせい)の要因について、「施設整備や運営体制」などの施設側の課題と、「制度設計や利用条件」など制度面の課題、それぞれの観点から市としてどのように課題を捉(とら)えているのか伺います。
施設整備については、人口減少社会に突入し、こどもの減少が見込まれる一方で、共働き世帯の増加によるニーズの変化もあることから、児童クラブ申請者数の推計が困難であり、必要性を的確に見極める難しさが課題であると考えています。 次に、制度面については、例年、夏休み明けに退所する児童が増加し、定員を割り込む児童クラブも発生する等、事業運営が難しいことが課題であると考えております。
4問目:
「子ども・子育て支援事業計画」や、これまでの待機児童対策の取り組みの振り返りを踏まえて、現時点でどの程度の改善効果が見られていると評価されているのかを伺います。
現行の対策の策定に先立ち、令和4年度に行った推計において、2年度の定員数1,928名に対して、7年度までに229名の定員増の必要性を見込んでおりました。実際には、7年4月1日現在、98名上回る327名の定員数増加を達成しており、推計値を上回ることができたことから、 一定の効果があったものと考えております。
5問目:
夏季休暇期間中に実施される「サマースクール」などの代替事業について、実施校数、利用者数、運営状況や課題等を踏まえた本市としての事業の位置づけを伺います。
サマースクール等は、小学校の長期休暇期間中に、児童クラブに通所していない小学3年生から6年生を対象に、実施している事業でございます。 令和6年度の実施状況につきましては、民間施設活用の東海岸教室と、学校施設活用の鶴嶺教室の2か所で実施しており、 利用者数は、東海岸教室が60名、鶴嶺教室が37名、合計で97名となっています。 なお、課題といたしましては、市内全域を範囲としていることから、移動の点で利便性の良い実施場所の確保があげられます。
6問目:
こうした事業の情報発信(周知)については、市民側が自ら情報を探さなければたどり着けないとの声もあります。情報格差の是正に向けた取り組み状況を踏まえた、今後の改善方針について伺います。
令和7年度実施予定のサマースクールの具体的な周知につきましては、市公式ホームページへの掲載をはじめ、市公式 LINEアカウント等、子育て世代を考慮した情報発信媒体を活用しながら実施したところです。 次年度に向けては、事業に参加を希望される市民の皆様に、十分に情報が届くよう、ホームページの掲載方法の見直しや、 広報紙の活用等、より一層、目に触れやすく、伝わりやすくなるよう周知方法を工夫してまいります。
7問目:
放課後児童クラブに入所できなかった児童が「ふれあいプラザ」を利用するケースがありますが、学校やプラザとの間での情報共有など連携体制についてどのように図られているのか伺います。
公設民営の児童クラブでは、各クラブで地域連絡会を設置しており、学校や地域の関係者の方にご参加いただき、顔の見える関係性を構築しながら円滑な運営に努めております。 また、小学校ふれあいプラザとの連携については、小学校ふれあいプラザ運営協議会に、公設民営児童クラブの指定管理者が参加し、情報共有や連携を図っております。
8問目:
これまで市内18校で実施されてきた「ふれあいプラザ」が、現在17校となっていることについて、減少に至った経緯や背景にどのような課題があったと認識されているのかを伺います。(今後の改善策についても)
小学校ふれあいプラザは、令和6年度まで市内18校で実施してまいりましたが、鶴が台小学校の「プラザ鶴が台」が、利用者や、子どもたちを見守るパートナーの減少を主な要因として、7年度から休止しております。 本事業につきましては、全般的に、地域ごとの特性の把握や担い手の確保が課題となっていることから、引き続き、地域の皆様と今後の対応について協議を進めていくことが大切であると考えております。
(2)待機児童解消に向けた取組について
2問目:
今後の見通しとして、待機児童数を一定数以下に抑えるための数値目標や、達成時期などを踏まえた計画的な設定について伺います。
待機児童解消に向けましては、令和7年度までを対象期間とする現行の対策の下、取組を進めてまいりましたが、今後も継続的な対策が必要であることから、これまでの取組を検証しつつ、今後の人口動態や社会情勢、ニーズの変化、財政状況等を見据えて、8年度以降の数値目標や達成時期等を含む実効性のある方針を、新たに策定してまいります
3問目:
待機児童対策においては施設整備に加えて、支援員の確保や質の維持も極めて重要と考えます。人材確保について現状を踏まえた課題について、市の見解を伺います。
市内で運営している児童クラブにおいては、現在、必要な人材は確保されているものと認識しております。 児童クラブ支援員の資質については、次期の指定管理者選考に際し、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能を高めるための研修の機会確保等、人材育成について事業者に求めています。 また、市といたしましても、引き続き、県が実施している研修の情報を児童クラブに提供するなど、スタッフの資質の向上を図ってまいります
4問目:
待機児対策の一環として、小学校ふれあいプラザ事業との連携も推進してきたはずですが、それがあまり成果に繋がっていないように感じます。(どこに問題があって)どう改善すべきと考えているのか伺います。
小学校ふれあいプラザ事業につきましては、実施校の減少をはじめ、開催数や参加者数につきましても一進一退の状況であり、背景として、プラザ実施に関わる担い手不足が主な原因として考えられます。このことは短期間での解決は難しく、プラザ運営協議会の場などを捉え、地域ごとの実情を踏まえながら、地域の皆様と一 緒に、丁寧な対策の検討が必要と考えております。
(3)指定管理者の指定について
2問目:
指定管理者によって、入退会手続きや連絡方法等のデジタル化の進み具合に差があるとの声もあります。市全体での運営基準が統一されていないことによる混乱も懸念される中、こうした差異の把握・評価を踏まえ、今後の標準化に向けた方向性を伺います。
指定管理者のうち、1事業者が令和6年度中に、7年度入所に係る電子申請システムを導入しております。 「デジタル化」の推進につきましては、国の方向性や重要性を踏まえ、次期指定管理者の募集要項でも、新たに「デジタル化の方策」に係る提案を求めているところでございます。 今後、次期指定管理者として選定された事業者とは、サービ ス内容に地域差が生じないよう留意しながら調整を進め、利便性向上に取り組んでまいります。
3問目:
本市では、これまで放課後児童クラブの指定管理区域を市内5ブロックに分け、地域特性を踏まえた運営が行われてきました。しかし、令和8年度4月に向けた指定管理者の募集要項には、「東部ブロック」「西部ブロック」の2ブロックに再編され、大きな方針(ほうしん)転換(てんかん)が図られています。このブロック再編の理由や背景について、市の見解を伺います。
これまでの指定管理者による事業運営の状況を検証した中で、児童クラブの継続的・安定的な運営や、一定程度のサービス水準確保の視点から前回の5ブロックを活かしつつ、最大でも現行の2事業者までが妥当であると考え、公募については2ブロックにしたものでございます。
4問目:
また、今回の募集要項では応募法人に対する地域制限が特段設けられておらず、結果として1法人が市全域の運営を担うことも可能となっています。
仮に特定の1法人が全ての区域を担うことになった場合、市としてはどのような(メリット・デメリットを想定し、それをどのように)評価をされるのかを伺います。
選定の結果として指定管理者が1事業者となる可能性は、これまでと同様でございますが、民間事業者の創意工夫、ノウハウを生かして住民サービスの向上と管理運営の効率化を図るという制度の目的が達成されると判断した結果であり、選定される指定管理者の数によって、事業運営に影響はないものと考えております。
5問目:
5年前の指定管理者公募の際には、教育・保育提供区域に準じ、5ブロックでの分割公募によるメリットとして、地域特性を踏まえた提案が期待できることと、競争性の担保による質の向上を目指すために、児童クラブを複数の事業者が管理運営できるようにしたいといった説明があったと記憶しています。今回の公募内容はその説明と矛盾しているのではないでしょうか。なぜ市の考えが変わったのか見解を伺います。
2ブロックによる公募にあたっては、これまで同様、各地域の特性を前提とした「地域等との連携」を重視し、提案を求める項目として設定しております。 競争性についても、事業者を広く募集する公募制を採用したうえで、選定する過程において担保する仕組みとしていることで、児童クラブの質の向上につながっていくものと考えております。
6問目:
「サマースクール」などの長期事業対策は、待機児童対策としても重要な取組であり、少なからず指定管理者の選定結果も影響するのではないかと考えられますが、公募にあたってどのような検討をされたのか伺います。
サマースクール等長期休暇対策事業につきましては、児童クラブ運営とは異なる事業であり、次期公設民営児童クラブ指定管理者選定による影響が想定されないことから、特段の検討は行っておりません。サマースクール等の長期休暇対策事業については、事業の必要性を十分に精査したうえで、実施場所や実施方法も適宜検証しながら、今後も継続的に実施していきたいと考えております。
7問目:
今回の指定管理者選定では、新規参入事業者の可能性を含め、事業者の入れ替わりが想定される状況にあります。こうした中でも、子どもたちにとっては日々通い続ける安心できる居場所であり、保護者にとっても信頼して預けられる環境の継続が何より重要です。今後、市としては、指定管理者が変更になった場合であっても「変わらない安心感」を子どもたちと保護者に提供できるよう、制度の柔軟性と運営の質をどのように両立させていくお考えか、市の基本的な姿勢を踏まえた今後の取組方針を伺います。
現在の指定管理者に対しては、協定書の中で引継ぎや視察の受け入れ等の協力について定めています。 また、次期指定管理者については、指定管理者募集要項において、開始時にスムーズに業務が行えるよう引継ぐとともに、 事前に市や関係する機関・団体等と連携や調整をすることとしています。 指定管理者が変更となる場合は、児童や保護者に影響が生じることがないよう、市といたしましても、新旧の指定管理者と 連携・調整し、円滑な業務の移行に取り組んでまいります。

メッセージ受付中!
茅ヶ崎のまちのこと、市議会のこと、みなさんの暮らしの中でのお気づきのことなど、
何かありましたらお気軽にお問い合わせください。
内容をしっかりと拝見し、お返事させていただきます。